かくして、同じ頃、サンガララの本陣では、いよいよ間近に迫り来た敵軍を迎え撃つべく緊急に推し進めた臨戦態勢の準備が、ほぼ完了したところであった。
出陣を前にして、ミカエラは己の天幕にイポーリトとベルムデスを呼び寄せた。
彼女は、己自身で作り上げた女性用の戦闘衣を纏い――頑強な布地のスカートを膝下ほどに短く縫製し、脇には鋭利なスリットをほどこして機動性を増している――その上には、分厚い皮革の胸甲を身に付け、既に武装を完了している。
さらに、足には皮製の戦闘ブーツを履き、その腰には重厚な長剣と銃が装着されていた。
長く豊かな黒髪も、今は硬く結い上げられている。
雄々しい立ち姿で二人を前にしたミカエラは、まず、イポーリトの後方に跪いて控えているベルムデスへと視線を向けた。
「ベルムデス、此度はイポーリトが世話になります。
どうか宜しく頼みます」
「はっ!
お任せくださいませ」
ベルムデスは、いっそう身を沈め、ミカエラに深く礼を払った。
そんな老練の重臣の傍へ、ツッと、歩み寄ると、彼女もまた相手の傍に膝をついた。
「ベルムデス、そなたには、その身の若き頃から今の歳になるまで、実に長い時の中を、優れた智慧と勇気によって我らを支え続けてきてくれました。
そなたは夫の父母の代より仕え、この反乱においても、準備段階から我らに常に適切な助言を与え、夫が敵の手に落ちた時には危機に瀕したマリアノを庇護してくれたこともありましたね。
充分すぎるほどの働きをしてきてくれたそなたを、もうそろそろ安寧に満ちた平穏な生活の中に解放してあげたいと願っていたのに。
それどころか、今、このような形で、これまで以上の危険の中に、その身を投じさせることになろうとは……」
「ミカエラ様、勿体無いお言葉でございます…!
そのようなお言葉を賜り、この人生、もはや思い残すことはございません」
深々と平伏したベルムデスの肩が小刻みに震えているのに気付き、ミカエラも、そして、傍で見守っていたイポーリトも、思わず胸が熱くなる。
「いいえ。
必ずや、イポーリトと共にそなたも生還するのです!!
そして、そなたには、この反乱の行く末を見届けてもらわねばなりません」
「はっ…!!」
「必ず、ですよ」
そう言って、ミカエラは、声を詰まらせるベルムデスの腕に優しく触れた。
それから、彼女は、いつしか己と同様にベルムデスの傍に膝をついていた皇子の方へと向き直る。
イポーリトは、父トゥパク・アマルが戦闘時に纏っていたのと良く似た黒生地に金糸の入った戦闘服に、頑強な皮の胸甲をあてがい、帯剣と拳銃で武装していた。
肩口で短マントを巻きとめている黄金の留め金に、絹糸のような髪がサラリと触れている。
父母に似て長身のイポーリトは、その大人びた風貌とあいまって、本格的な正装を纏うと、いっそう年齢が上に見え、16〜17歳の青年兵と見紛うほどであった。
「母上、それでは、行って参ります」
凛々しく出陣の挨拶を述べた息子を、ミカエラも怜悧な瞳で真っ直ぐに見つめた。
「イポーリト、そなたと共に行く主力部隊の者たちは、そなたが彼らと共に危険な戦線に加わって戦うことで勇気を得、力を得ることでしょう。
戦場でのそなたの心意気を、そなたの姿を、そなたと共に行く者たちが常に見ていることを、よくよく心得て臨むのですよ。
如何に若年とはいえ、戦場に出る以上、そなたは、もう一人前の兵士。
それどころか、父上の嫡男としての立場上、そなたは統率者としての身の振り方さえ求められることでしょう。
たとえ如何なる状況にあろうとも、そなたと共にある全ての兵たちの命を預かっているのだということを、ゆめゆめ忘れてはなりません」
指揮官としての面持ちで厳然と語るミカエラの言葉に、イポーリトは、もはや後戻りのできぬ険しい道程に自ら踏み出してしまったのだということを、現実のものとして痛感していた。
だが、それでも、よもや揺るぎのない覚悟の表情は変わらない。

「はい、母上。
良く分かっています」
「そなたの武運を祈っています、イポーリト」
「母上も、どうか…どうかご無事で…!」
ミカエラは頷くと、己の懐から、ハンカチほどの大きさの、美しい黒ビロードの布を取り出した。
「イポーリト、そなたにこれを」
「それは?」
イポーリトが驚いて、ミカエラに似た美しい目元を大きく見開く。
「これは、そなたの父上が、かつて最初の決戦で勝利を上げた際に纏っていた衣服の一部です。
これを身に着けてお行きなさい。
必ず父上がそなたを護ってくれましょう」

そう言って、ミカエラは手ずから、その美しい布をイポーリトの右の上腕に結びつけた。
「母上…ありがとうございます……!!」
母を見上げるイポーリトの瞳も、今は母としての面差しで微笑むミカエラの瞳も、大きく揺れている。
そして、そのような二人を見守るベルムデスの目尻にも、微かに光るものが滲みだす。
その時、天幕の一隅に置かれていた棚の方で、ガタンッと、何かがはずれるような大きな音がした。
ハッと、三人がそちらを振り返る。
すると、重要な品々が納められているその棚の中央に立て掛けられていたはずの黄金の笏杖が、独りでに床に転がり落ちていた。
しっかりと留め金と紐で固定していたはずなのにと、瞳を大きく見開く三人の目の前で、その笏杖は、今度は、ゆっくりと平らな床を転がり始めた。
まるで何かの見えざる手によって運ばれているかのように、カラカラと転がり来る黄金の笏杖――それは、やがて、イポーリトの足元でピタリと止まった。
「……――!!」
ミカエラもイポーリトも、そして、ベルムデスもまた、暫し息を詰めたまま、少年の足元で輝く笏杖を見下ろすばかりである。
黄金の笏杖――1メートルは優に超える長さと重量感を備えたその笏杖には、太陽神をモチーフとした優美で精緻な彫刻が施され、上部には、上質なエメラルドを主とした宝石類がちりばめられている。
それは、代々インカ皇帝の皇位継承者に受け継がれてきた秘宝であった。
インカの創造神ビラコチャも、この笏杖を手にした姿で言い伝えられているように、それはインカの神々の象徴であり、且つまた、神々の御子とされたインカ皇帝の象徴でもあったのだ。
この反乱が幕を開けた時、トゥパク・アマルが故郷のトゥンガスカで最初の演説を行った際にも、そして、聖都奪還の悲願を懸けたクスコ戦に臨むにあたって民衆を鼓舞した際にも、彼の手には常にこの笏杖があった。
今、さらに陽が傾き、明るさの薄らいだ天幕の中で、なお燦然と輝き渡るその黄金の笏杖をイポーリトは恍惚と見下ろした。
彼は、まるで何かに憑かれたように、足元へと手を伸ばしていく。
そして、煌々と光輝く笏杖を力強く握り締めた。
(…―――父上!!)

それから間もなく、イポーリトたち主力部隊は、ミカエラたちが守る本陣を出陣していった。
このイポーリト軍を成す兵数は、専門兵と義勇兵を合わせて約千5 百。
この軍に加わった義勇兵は、実戦に耐えられる者たちのみが選ばれた。
それでも、その兵力は、敵の約3千に対してほぼ半数にすぎない。
他方、本陣に残ったミカエラ軍を成す兵力は、実戦に耐え得る精鋭兵が約3百、そして、訓練中の義勇兵が約2百であった。
今、本陣に残ったミカエラの元には、敵情視察のために放たれた斥候たちが次々と馳せ参じては、敵軍の動きを逐一報告していく。
しかし、この時に至っても、トゥパク・アマルからの返答の伝令は皆無なままだった。
実際、それも無理からぬことではあった。
いかに高速の伝令鳥の強靭な翼をもってしても、これほどの長距離を、この短時間で往復などしようもないことは、もとよりミカエラも承知の上である。
そもそも、己の放った伝令鳥が、トゥパク・アマル陣営まで無事に辿り着いたのかどうかさえ定かではなかった。
否、たとえ、無事に辿り着いていたとしても、いかにトゥパク・アマルとて、あのような遠隔地から、一体、何ができようか。
しかも、もう、全く時も無い。
もはや、敵軍は、いつ姿を現してもおかしくないほどの至近距離まで迫っているのだ。
(当地にいる我らの手で、この局面を乗り切る以外に道は無い…!)

高地の冷風を顔に吹きまつわらせながら、鋭利な矢尻のような黒耀石の瞳で、ミカエラは周囲の霊峰を見渡した。
本陣は峻厳な断崖上に布陣しており、その左右は、如何に敏捷な獣でさえも這い登ることが不可能なほどの切り立った断崖絶壁――敵に側面を突かれることの無い、堅固な自然の要害を成している。
一方、背後は、やはり急勾配ながらも人が集団で移動できる程度の傾斜が保たれており、本来であれば、いざやという場合の退路となるべき方面であった。
しかしながら、その途上の河川が氾濫している今、もはやインカ軍に退路は無く、既に周知の通り背水の陣となっていた。
だが、逆に見れば、敵方も裏山から河川を渡ることは不可能なわけであり、今なら敵に背後を急襲される危険も無かった。
従って、敵方が攻め上ってくることの可能な方面は、厳重な武装を敷いた正面の一方向に絞られてくる。
しかも、その限られた敵の進軍経路には、本陣に近づくほど堅牢さを増す、城堀の如く塹壕が、以前から深く堀り巡らされていた。
かくして、本陣を背に、敵軍が唯一登り得るであろう正面眼下に連なる数メートル幅の隘路(あいろ)に向いて敢然と迎撃態勢を敷く自軍の兵たちを、ミカエラは強い光を湛えた眼差しで見つめた。
全ての兵たちは、強靭な皮製の胸甲を纏い、得意とする武器で頑強に武装している。
約30門の大砲には、それぞれ砲撃に熟練した専門兵がつき、いつ敵軍が現れようとも、すぐさま砲弾の雨霰を見舞えるよう、敵の進軍してくるであろう斜面に向けて完璧に照準済みである。
しかも、それらの各大砲の傍には赤々と燃える釜が備えられ、そこでは砲弾が熱く焼かれていた。
これによって、敵軍のどまん中に、高熱に燃え滾(たぎ)る熱弾を打ち込まんという算段である。

大砲の扱いなどひとつも知らず、せっかく戦果として手に入れた大砲を捕虜に操作させて無駄撃ちを重ねた反乱初期の頃など、もう遥かに昔のことのようだ。
今では、インカ側にも砲撃に習熟した専門兵が次第に育ってきており、その命中精度も確実に上がってきている。
また、他の専門兵たちは、敵側から奪取した銃やサーベル、そして、インカ族本来の武器であるオンダ(投石器)や種々の鈍器を手にして炯々と眼を光らせている。
さらには、まだ十分には武器を扱えぬ訓練中の義勇兵たちさえも、巨石を用いた落石攻撃や大木による落木攻撃を仕掛けんと身構えていた。
本陣に残った二人の皇子マリアノとフェルナンドも武装を済ませ、落石攻撃に加わらんと、己らの数倍以上もある巨大な石たちの傍に凛と立っている。
それら全軍の兵たちの前に、ミカエラは決然とした足取りで歩み出た。
絶世の美貌と美しい肢体を兼ね備えたミカエラが、戦女神の如く凛々しい武装を纏ったその姿に、思わず誰もが視線を釘づけられる。
いっそう傾きを増した朱色の陽光を浴びる彼女の姿は、その高貴で勇壮なオーラとあいまって、まるで燃え上がる炎の中に包まれているかのようだ。

恍惚と見入る兵たちの前で、彼女は神を仰ぐように太陽の方角へ礼を払うと、兵たちを超然と見晴らした。
そして、猛々しく声を上げる。
「皆の者よ!!
今や援軍も期待できず、逃げ道も無い我らにとって、この戦さ、勝って生き延びるか、敗れて死するか、二つに一つ。
我が夫トゥパク・アマルの伝令も、今しがた、わたくしの手元に届き、少数の兵力にもかかわらず、多勢の敵に立ち向かわんとしているそなたたちの高邁な精神と勇気とを、この上無く高く讃えておりました!!
そして、専門兵も義勇兵も、さすがに特別な精鋭たちを当地に残してきただけのことはあると!!
あの人に、そこまで言わしめたそなたたちの力を信じて、そなたたちが持てる力の全てを出し切ってくれることを願います。
必ずや、そなたたちに勝利の栄冠を!!
インカの神々のご加護がそなたたち全員の元にあらんことを!!」
「おお!!
トゥパク・アマル様が、我らのことをそのように!!」
ミカエラの言葉に呼応して、本陣を護る全軍の兵たちの間から、鬨の声と共に雄々しい「気」が漲った。

ミカエラは兵たちに頷き返すと、布陣する彼らの指揮を執るべく、敵を迎え撃つ臨戦態勢を敷いた断崖上の中央に力強く歩んで行く。
だが、実際のところは、トゥパク・アマルからの伝令など、彼女の元には未だ届いてはいなかった。
従って、彼の伝令が己の手元に届いたというのは、兵たちの士気を高めるためのミカエラの作り話であった。
しかしながら、生死の瀬戸際に追い込まれた兵たちにとって、トゥパク・アマルの言葉がいかに大きな影響力を持つか、これまでの反乱の過程を見れば明らかだった。
ミカエラは、遥か彼方にあるはずの海岸線へと、遠く視線を馳せる。
(この際、背に腹はかえられぬ。
勝利するためには、今は、どのような手段でもとらねばならぬ。
それに、もし、あなたが当地の今の兵たちの姿を目の当たりにしたら、きっと、わたくしが彼らに伝えたように言ってくださいますね?)
彼女は他の兵たちに悟られぬよう、一瞬、長い睫毛をサッと伏せた。
(あなた、どうか、わたくしたちを護って――!!)

その頃、イポーリトと共に本陣を出陣していた主力部隊もまた、既に布陣を完了していた。
続々と放たれる多数の斥候たちの報告によって、敵軍の進軍経路や進軍状況は、逐一、手に取るようにイポーリトの元に伝わってくる。
敵の進路と見定めた山間の隘路沿いの両翼に、岩陰や森林を利用して兵たちを潜ませた後、イポーリト自身も険しい横顔で草陰に身を沈めた。
転がり落ちそうな狭く急峻な斜面の連続に加え、踏み締める先から崩れ落ちかける足場の悪さから、此度の敵軍は殆どが歩兵であった。
実際には、山麓では騎兵も少なからずいたのだが、騎馬での進軍の困難さに、多くの馬が途中で乗り捨てられていたのだった。
徒歩にしろ、騎馬にしろ、革鎧などの軽歩兵はまだしも、鋼鉄の鎧を纏った重装備で登り来る者たちはひどく難儀しており、案の定、予想以上に進軍に時間を要していた。
とはいえ、敵軍は本陣に向って着実に攻め上ってきており、それら鋼色の大軍の不気味な強靭さと執拗さには、インカ軍の幹部たちも驚きと不安の高まりを禁じ得なかった。
だが、スペイン側にしてみれば、事態を知ったトゥパク・アマルが差し向けるかもしれぬ援軍の到達を恐れ、一刻も早く戦闘の決着をつけたいという思いもあったことだろう。

ジワジワと距離を詰めてくる敵軍を待ち受けるイポーリトの脇で、同様に身を潜ませながら斥候の報告に耳を傾けていたベルムデスが、思慮深気な口調で口を開く。
「イポーリト様、今のところ、敵軍は我々が見定めた通り、この隘路を攻め上ってきてはおりますが、予想以上に頑健な様子……」
「うん…!
こんなに急な山を登ってきて、もっと消耗しているかと思っていたのに…!」
そう答えるイポーリトは、どうにも高まる緊張を表に見せぬよう、先刻から懸命に己を律し、堪えていた。
だが、ベルムデスの言葉に、思わず不安気に眉根を寄せる。
「わたしも同じ思いでございます、イポーリト様。
こうなってくると、案じられるのは、敵軍が余計な脇道にそれて、我らがこうして待ち構える以外の経路から、本陣に迫ろうとすることです」
「え…!?」
イポーリトが驚きと困惑の表情で、サッと顔色を曇らせた。
「だけど、本陣に向かうには、この道を通るしかないんじゃなかったの?」
ピリピリと神経が逆立って緊張の強い皇子を宥め、そして、諌(いさ)めるように、ベルムデスは屈強な身を傅(かしず)かせ、真摯な面差しを相手に向ける。
「イポーリト様の御言葉の通り、確かに、本陣に至る道となると、この隘路しかございません。
ですが、人の踏み入ることの無い獣道、あるいは、獣道とすら言えぬような道無き道などでございましたら、皆無とは言えません」
そう語りながら見つめる視界の中で、イポーリトは真剣とも深刻とも取れる張り詰めた表情で、固唾を呑んでいる。
そんな皇子に、ベルムデスはさらに言葉を継いだ。
「敵方にまだ余力があるとなると、万一にも、そのような場所でも構わぬからと分け入って、迂回経路を取ろうなどと考えつかれては、我々としては厄介です」
「ああ、それは困る……!」
「はい。
そこで、イポーリト様、わたしに一計がございます」

近くに潜んでいるかもしれぬ敵方の斥候に留意してか、ベルムデスは声を潜め、皇子の耳元に顔を寄せた。
そして、低声(こごえ)になって、早口で囁く。
「ここにいる軍勢の中から、精鋭から成る小規模の別働隊を編成し、この道を下山させて、進軍してくる敵軍の正面に姿を見せてやるのです。
そうしておいて、一足早く、敵の前衛部隊と小競り合いを開始させてはいかがかと」
「だけど、そんな少数の兵力では、わざわざ打ち負かされにいくようなものじゃ…!」
声を低めながらも戸惑いの表情を隠せぬ皇子に、ベルムデスが深く頷き返す。
「確かに、イポーリト様の仰せの通りでございます。
そう、わざと打ち負かされに行ってやるのです。
つまり、偽装の敗退、でございます」
「――!
もしや、わざと負けて逃げながら、敵をおびき寄せるってこと?!」
「まさしく仰せの通りでございます。
少し戦って見せては敗退を装って退(ひ)き下がり、また戦っては退き下がる――そうしながら、敵の追撃を煽ってはいかがかと存じます。
さすれば、幾ばくかでも敵を今より消耗させることができる上に、予定通り、この道に敵軍を誘い込むこともできましょう」

ベルムデスの案に、いつしか引き込まれるように聴き入っていた皇子が、澄んだ漆黒の瞳を大きく瞬かせた。
「だけど、敵が本当にその手に乗ってくれるだろうか?」
「使い古された常套手段ではありますが」と、眼前の若い指揮官に礼を払いながら、べルムデスは老練な目尻に皴を寄せて、僅かに目を細めた。
「逃げる敵は追いたくなる――それは軍勢にとって、古今東西変わらぬ、抑えがたい習癖というものでございます。
増してや、此度の敵軍は、逃げ場も無い劣勢な我らが及び腰になっていると期待しておりましょうから、逃げ惑う姿を見せてやれば、我が意を得たりとばかりに追撃してくることでございましょう。
とはいえ、この策は、あくまで、この隘路に敵を引き入れるための小手先のこと。
もっと肝要なのは、その後、どこまで戦かっていけるか、ということでございますが……」
かくして、早急にベルムデスの作戦を実行に移すべく、厳選された精鋭の別働隊が下山していく姿を見送るイポーリト軍もまた、当地の地形においては、騎兵よりも、むしろ難所での機動性の高い歩兵が部隊の殆どを占めていた。
陽の傾きと共に、ますます強い冷気を孕んだ風が、険しい山々の峰をビョウビョウと音を立てて吹き過ぎていく。
その風の中で、イポーリト自身も、それら歩兵たちに混ざって息を殺し、懸命に気配を消そうと試みていた。
だが、必死に平静を装うほどかえって動悸は速まり、無意識にサーベルを握り締める指には、不自然な力がこもらずにはいられない。
反乱開始前、まだ幼かったイポーリトは、かのアンドレスのようには特別な武術訓練は受けていなかった。
それでも、父トゥパク・アマルから、小さき頃より基本的な剣の指南は受けており――最も、トゥパク・アマルから見れば、まだほんのさわり程度というところであったろうが――、しかし、今は、それを頼りにするしかなかった。
増してや、銃など、曲がりなりにも腰に装着してきてはいるものの、人に対して放ったことなど、ただの一度も無い。

あれほど勢い良くミカエラに啖呵を切って出陣してきたというのに、実際に敵兵たちと交戦せねばならぬ時が刻一刻と迫り来るにつれ、イポーリトは早鐘の如く打ち鳴る胸の鼓動を止めることができなかった。
周囲に悟られぬよう、ガクガクと震えのきそうな足元を力一杯に踏み締めて堪えているが、それも武者震いというより、恐怖と緊張によるものだと自ら悟っていた。
(こんなふうに無理を押して主力部隊に加わってきてしまったけれど、僕がいることで、かえって皆の足手まといになりはしないだろうか……?!)
そんな不安な思いが暗澹と胸中に広がっていく。
だが、その瞬間、イポーリトの脳裏に、突如、あの去り際のシモンの言葉が大音量で鳴り響いた。
『甘ったれるな!!
さっき、君は、この陣営を自分の手で守ってみせると、あれほどハッキリと言っていたじゃないか!
あれは、ただの口から出まかせか?』
『……――!!』
『本気でああ言ったのなら、自分の力で、それを証明してみせろ!!
しっかりと見届けてやる。
――遠くからな!!』
イポーリトは険しい眼光で、グッと、乾いた唇を噛み締めた。
不意に、怒りとも、闘志ともつかぬ、これまで感じたことの無い激しい感情が、心の奥底からメラメラと炎のように燃え立った。

(いかにも僕たちに協力してくれるような素振りをしながら、いざ僕らが窮地に立ったら、手の平を返したように見放していったあなたに、僕の気持ちの何が分かるって言うんです?
それも、見放すだけではあきたらず、懇願する僕に、わざわざ乱暴な言葉を投げつけていった……!
ああやって、僕をわざと奮い立たせようとしたのですか?
見捨てて去っていくようなあなたの言葉が、僕の力になるとでも思ったのですか?
馬鹿げてる……!!
僕なら、あなたみたいな振る舞いは絶対にしない。
どんなに仲間の振りをしたって、あなたは、所詮、スペイン人だったんだ。
父上があなたを認めても、僕はあなたを許せない……!
必ず…生きて、必ず、あなたを見返してやる!!)
一方、激しく揺れ動くイポーリトの胸中をよそに、そんな皇子を擁した主力部隊の兵たちの士気は、自ずと高まらずにはいられなかった。
「イポーリト様は、ミカエラ様が止めるのも振り切って、我らとご同行してきてくださったそうだ!」
「ああ、我らだけを危険な目に合わせることはできないと、ミカエラ様の前に土下座までされたとか!!」
イポーリトの出陣までの経緯は、光の波紋が大きく広がりゆくように、大なり小なりの美談を伴いながら、早くも全軍の兵たちの間に浸透していた。

イポーリトとミカエラのやり取りがこれほど迅速に全兵に行き渡った背景には、実は、あの場に参集していた隊長たちが、兵たちの士気を高揚すべく大々的に噂として流したといういきさつがあった。
そして、あの時、ミカエラの前に進み出てイポーリトの主力部隊への参戦を進言した、かの隊長は、今、ベルムデスと共にイポーリトの左右を護っていた。
彼は、死戦を前にしながらも、力強い精気を漲らせている兵たちを逞しい面差しで見渡しながら、己の隣で懸命に自らの心と格闘している年若い指揮官に、深い鳶色の双瞼を向ける。
「イポーリト様の勇敢なるご決断とご同行によって、兵たちは大いに気概を高めております」
「そうか。
ならば、僕も来たかいがあって、嬉しいよ」
明らかに緊張を滲ませながらもトゥパク・アマルに似た面差しで微笑むイポーリトに、その隊長も笑みを返し、厳めしい体躯を傅(かしず)かせて礼を払う。
貫禄がありながらも、若々しく精気溢れる風貌をした褐色の兵である。
背を覆う豊かな黒髪――敵の刃から背後を護るためであろうが――と、銃と共に腰に提げられた、いかにも切れ味の良さそうな大振りの半月刀が目を惹き付ける。
「わたしは、この主力部隊の各部隊長を統率するオルティスと申す者。
この後、イポーリト様の手足となって働かせて頂きます」
そして、今一度、精悍な笑みを見せて、続ける。
「イポーリト様にとりましては、此度が、実質的な初陣にございますな。
なれば、なおのこと、何としても勝利で飾らねばなりますまい!」
「え、初陣――?」
言われたイポーリトの方が驚いたように目を瞬かせ、それから、その力強くも新鮮な響きを心で反芻するようにして呟いた。
「そういえば、トゥンガスカの本陣戦で少しだけ戦場に出たことはあったけれど、あれは、ほんの形だけだった。
そうか、この戦いが、僕にとっては初陣か!!」
にわかに高まりゆく気力と興奮のために、微かに紅潮した横顔を輝かせて言うイポーリトの姿に、彼を挟んで左右に身を傅かせるオルティスとベルムデスは、黙って微笑み、目で頷き合う。
「ありがとう、オルティス。
ならば、こんなに戦いがいのある初舞台を用意してくれた敵軍に、感謝しなくちゃいけないな」
いつものイポーリトらしい笑顔を取り戻し始めた様子に、オルティスは目を細めた。
「この状況で、それだけ仰られるのならば、たいしたものです」
これまでも本陣で傍近く見守り続けてきたオルティスにとって、身分や立場は遥かに高位とはいえ、実は、懸命に背伸びをし、葛藤もし、そして、危なっかしいほど真っ直ぐで――そんな、どこにでもいそうな少年イポーリトに、弟を見るような愛しさを密かに抱いてもいたのだった。
やがてオルティスは、隊長としての真面目な表情に戻って、身を低めながらイポーリトを見上げた。
「ベルムデス様の作戦によって、敵兵たちがこの道に誘い込まれてくれば、いよいよ本格的な決戦でございますな」
イポーリトも、やや緊張した面差しに戻り、素早く頷いた。
「ああ。
スペイン軍が姿を現したら、道のこっち側に潜んでいる僕らと、道の向こう側に潜んでいる味方の兵とで、挟み撃ちにするんだよね?」
「はい。
とはいえ、敵の大軍は、この狭い道を、長々しい隊列を成して登ってくることでありましょう。
それ故、敵の前衛部隊から後衛部隊まで、余すことなく、まずは、この眼下の隘路に十分に引き入れなければなりません。
そして、恐らく、敵方も、我々が挟撃してくることを予測して、厳重に備えているはず。
ですから、我らへの警戒に対する敵の気をそらすことも肝要です」
皇子は、神妙な表情で、また頷いた。
「うん。
だから、作戦で取り決めた通り、敵の前衛部隊が母上の護る本陣の断崖下まで辿り着くまで、僕たちは攻撃を開始せず、このままここに潜んでいるんでしょう?」
オルティスは鋭い眼光で、「はい」と頷く。
「我らより先に、まずミカエラ様の精鋭部隊が敵の前衛部隊に攻撃を開始し、敵の意識を本陣に引き付けます。
そうしている間に、敵の隙を突いて、ここに潜む我らが、敵の主力部隊と後衛部隊を側面から伏撃するというのが当初の計画でございます。
ただ、その方法には、実は気がかりなことが――」
オルティスが何かを言いかけた時、山の遥か下方から、パンパンと空気を弾くような渇いた発砲音が、冷たい風に乗って流れ来て、微かに鼓膜を震わせた。
イポーリトは反射的に身を固め、思わず生唾を呑みくだす。
(敵をおびき寄せに行った別働隊が、もう交戦を始めたんだ……!!)
このような距離を隔てて、あり得ないことなのに、火薬の匂いまで届いてきそうな錯覚を覚え、皇子はサッと顔を強張らせた。
「下山して行った別働隊のみんなは、スペイン軍との戦いを始めているみたいだ。
みんな、無事でいてくれるだろうか…?」

痛々しいほどに見開かれた漆黒の瞳を見つめながら、オルティスが沈着な眼差しで応じる。
「特に戦さ慣れした精鋭を厳選して行かせています。
どうぞご案じなさいますな。
それより、先ほどの話しの続きでございますが、あの作戦には少々心配な点がございます」
「心配な点?」
今度は、イポーリトが、オルティスの深い鳶色の瞳を不安気に覗き込んだ。
オルティスは、そのような皇子に礼を払いながらも、忌憚の無い口調で続けていく。
ただし、その声音はひそやかで、どこに潜んでいるか分からぬ敵方の斥候への注意を怠らない。
「本陣では、ミカエラ様の精鋭部隊が、敵の前衛部隊を引き付けてくれましょう。
先ほどイポーリト様が仰いました通り、その隙に敵軍を奇襲挟撃するというのが此度の作戦ですが、なにぶん敵の隊列は長い。
ミカエラ様たちの陽動作戦は敵の前衛部隊には効き目がありましょうが、主力部隊や後衛部隊にまで効果をもたらすことは難しいでしょう。
それに、ミカエラ様たちに、敵の猛攻があまりに集中しては、危険です。
あの本陣の正面は塹壕や砲台で武装され、兵も選り抜きの者たちが残ってはいますが、いかんせん兵力が少ない。
その上、あそこの約半数は、戦闘経験の無い訓練中の義勇兵たちです。
もし正面の守りを突破されてしまうようなことがあれば、本陣の少数部隊で持ち堪えるのは非常に厳しいと言わざるを得ません。
それに、ひとたび敵に本陣への進攻を許してしまえば、ミカエラ様や残っておられる二人の皇子様たちの御身も多大な危険に晒すことになってしまう。
万一――ミカエラ様たちが囚われ、人質とされてしまうようなことがあれば、我ら主力部隊の動きも、その時点で全て封じられてしまうことになりましょう…!」

己の言葉に大きく瞳を揺らめかせている皇子を支えるように、その真摯な双瞼で見つめながら、オルティスはさらに続けていく。
「ですから、我ら主力部隊は、何としても本陣への敵の進攻を阻止しなければなりません。
そこで、イポーリト様に、ご提案があるのです」
「提案?」
「イポーリト様には、手勢を引き連れて主力部隊を一時的に離れて頂き、ミカエラ様とは反対方面から敵を陽動してはいかがかと」
「――僕も陽動を?」
「はい」と、艶やかな低い声で応じて、オルティスはさらに身を低めた。
「主力部隊をここに潜ませたまま、イポーリト様は敵の背後の断崖上に回り、ミカエラ様と敵方との交戦の状況に応じて、背後から敵を陽動してはいかがかと。
さすれば、ここの伏兵はそのままに、ミカエラ様の本陣のみに敵の猛攻が集中するのを避けることができるやもしれません」
「敵の背後?
背後になんて、簡単に回らせてはくれまい」
「もちろん真後ろとはいきませんが、敵の進軍してくるこの隘路そのものが四方から幾重にも断崖に囲まれているのです。
敵の目を引き付けることが目的ならば、何とでもなりましょう」
息を詰めるイポーリトの横では、ベルムデスが、その老練な面差しをオルティスに注いでいる。
そのベルムデスの視線にも、オルティスは深く身を傾けて礼を払った。
やがて、イポーリトは、思慮深い横顔で相手の顔をひたと見据えた。
その大人びた風貌は、到底、本来の年齢には見えない。
「オルティスの言いたいことは、良く分かった。
確かに、母上たちの護る本陣に敵の攻撃が集中するのは、とても心配だ」
そう言って、右腕に結ばれた父トゥパク・アマルの布を、無意識にギュッと握り締めた。
「それに、ここが、どんなに地の利を得ているとはいえ、敵も僕らの急襲に備えているのは、オルティス、君の言う通りだと思う。
それを逆手に取って、こちらが突撃しいく瞬間を捉えて一掃しようと、いつでも引き金を引けるように、向こうこそが虎視眈々と狙い定めているかもしれない…!」
「イポーリト様の仰せの通りです。
無謀な突撃を敢行して奴らの掃射を浴びれば、我らはひとたまりもありません。
たちまち辺りは、インカ兵の屍の山となりましょう。
それに、斥候たちの報告では、このような山岳地にもかかわらず、敵軍は多数の野戦砲を持ち込んできている由、いっそう予断はなりません」
そう苦々しく言うオルティスの輪郭に、一瞬、深い影がよぎる。

「なれば、我ら主力部隊は、あやつらの銃や野砲に物を言わせる前に、一気に白兵戦に持ち込まねばなりません。
敵味方入り乱れての乱戦となれば、奴らだって、そう安易には銃も大砲も使うことはできますまい。
増してや、これからいっそう陽は翳り、誤って味方を撃つ可能性は、さらに高まるでしょうからな」
相手の言葉に、イポーリトも俊敏に同意した。
「分かった。
オルティス、君の提案に乗ろう」
皇子の言葉に、今一度、オルティスは深く礼を返し、それから、サッとベルムデスへも視線を馳せる。
ベルムデスは、沈着な光を湛えた目で、黙って頷いた。
そんなベルムデスにオルティスは再び目礼し、皇子に屈強な体躯を決然と向けた。
そして、力強く言う。
「もちろん、わたしもイポーリト様と共に陽動部隊として参り、お傍にてお力添えをさせて頂きます」
「ありがとう、オルティス。
君がいてくれたら、僕も心強い!」
イポーリトの言葉に、オルティスは精悍な笑みを返す。
「勿体無い御言葉でございます。
他にも数十名程度のインカ兵を伴って行き、派手に火砲を見舞って、いかにもイポーリト様の背後に主力部隊の大軍が控えているかに見せかけてやりましょう。
敵の意識を我らに引き付け、こちらに陽動している隙をついて、その時こそ、ここに潜ませている真の主力部隊で敵の脇腹を伏撃するのです」

力強く頷くイポーリトにオルティスも微笑み、さらに眼光の鋭さを増して続ける。
「とはいえ、敵は多勢であるのみならず、此度の敵将ガルベス大佐は、あのスペイン軍総司令官バリェ将軍にも目をかけられてきた精鋭との情報も入っております。
こうして策を弄しても、どれほど対抗できるか全く予断はなりませぬが、なればこそ、手をこまねいているわけにはいきません。
ミカエラ様の軍と我らと、そして、両側面の主力部隊とで、敵を四方から包囲殲滅するほどの勢いで、攻めて、攻めて、攻め切っていかねばなりますまい!!」
かくして、本陣で迎撃態勢を敷くミカエラたちが見晴らす眼下の隘路に、ついに敵の前衛部隊がその姿を現した。
それらの敵軍は、偽装敗退を仕掛けたベルムデスの罠によって、インカ側の主力部隊が両翼に身を潜める狭隘な山道へと、着実に誘い込まれて来る。
今、敵軍の前方を、いかにも痛手を負わされて這(ほ)う這うの体(てい)で敗走しているかのごとくに装い――見事な擬傷行動を演じ切りながら、巧妙に敵を先導してくるイポーリト軍の精鋭部隊が駆け上ってくる。

このベルムデスの作戦については、ミカエラの元にも既に伝令が届いていた。
そのため彼女は大きく驚くことはなかったが、それでも思わず息を詰めて、眼下に展開する状況を見下ろしていた。
(敵に意図を悟らせず、ここまでおびき寄せてきた兵たちの技量、なかなかのもの…!
インカ兵たちにも、このような敵の裏をかいた行動ができようとは――)
半ば驚き、半ば感心しつつ、そして、微かに複雑な心境をも抱きつつ眺めやる彼女の視界の中で、しかし、迫り来る敵軍の放つ異様な威圧感と敵意に満ちた禍々しいオーラもまた、生々しく健在であった。
それらを睨(ね)めつけながら、ミカエラは、その冷厳たる目元を険しく聳(そび)やかせた。
金属の甲冑に身を固めた敵兵たちの連綿たる隊列が、日暮れ前の斜光を照り返し、不気味な鈍い光を放っている。
しかも、それらのギラつく長大な鋼色の連なりの随所に、黒光りする砲身が見え隠れしている。
「大儀なことよ。
野戦砲とはいえ、このような場所まで運んでこようとは…!」
刃のように鋭利なミカエラの横顔で、口元から苦々しい声が低く漏れる。
それら野戦砲は、通常の大砲に比して、口径も、全体的な形状も小型ではあるが、それ故、二輪の木製砲車に載せて、こうした険しい山岳の野戦地にも運び込むことができる。
しかも、斥候たちの報告によれば、敵軍が持参したそれら野戦砲は70〜80門をくだらない。
一方、敗退を装って走るインカ兵たちの追撃に躍起になっていた敵兵たちは、不意に、眼前の断崖上にミカエラの姿を認めた。
敵兵たちの間から、どよめきと共に、荒々しい鬨の声が湧き上がった。
それと同時に、その攻め上る足をさらに加速させる。
かたやミカエラは、それを挑発するかのように、自ら他のインカ兵たちより数歩前に歩み出て、断崖上から敵兵たちを大きく覗き込んだ。
夕陽を浴びて、彼女も周囲の山々も、燃え立つような緋色に染まっている。
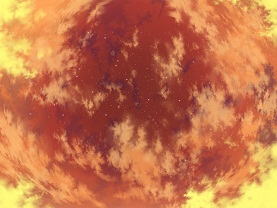
「いたぞ――!!
トゥパク・アマルの妻、ミカエラ・バスティーダスだ!!
あの者を捕えた者には、莫大な報奨金をはずむぞ――!」
敵軍の将校らが兵卒たちを煽り立てる罵声が山々に木霊し、ハッキリと聞こえてくる。
が、敵兵たちの足がさらに勢いづいた次の瞬間、土砂のようなものが大きく崩れ落ちる轟音と共に、宙を貫く悲鳴が山間に響き渡った。
と同時に、茫漠たる土煙が、数メートルの高さまで立ち昇る。
そして、一瞬の静寂の後、その音の方角から、無数の悲痛な呻き声が、地底から滲み出すように湧き上がった。
他方、本陣を敷く断崖上には、強風にのって漂い来る砂塵の中、何事も無かったかのように、その美しい長身の背筋をスラリと伸ばして立つミカエラの姿があった。
彼女は、能面のごとき表情で、ただ瞳だけを動かし、それら敵兵たちを冷然と睥睨した。

次第に砂埃が晴れゆく視界の中で、眼下には、大地に空けられた巨大な溝の中に落ち込み、折り重なったまま身動きできずにいる敵兵たちの無残な姿が見える。
彼らが身に纏った重々しい甲冑は、互いを押し潰し合い、もはや凶器や足枷以外の何物でもない。
あるいは、まだ体の自由が利く者たちは、我先に溝から這い出さんと、味方の兵さえ乱暴に踏み台にしながら蠢き回っている。
先述のごとく、この陣営の周囲には何層にも渡る深い塹壕が掘られているが、インカ兵たちは、その塹壕の上に枝木を渡して土をかぶせ、人工の落とし穴を仕掛けていた。
その一層目に、突撃をしかけた敵の前衛部隊の一部が、もろに落ち込んでいたのだった。
砂塵に霞む危うい視界の中、前衛部隊の被ったいきなりの被害を前にして、敵軍の後続部隊が立ち往生しているさまが、断崖上から手に取るように見晴らせる。
その間にも、ミカエラは追撃の手を緩めない。
彼女は、不意に高々と上げたその腕を、力強く振り下ろした。
それを合図に、本陣のインカ軍から、多数の巨大な石木が次々と投げ落とされ始めた。
爆煙さながらの凄まじい土煙をあげながら雪崩落ちゆく無数の石木が、塹壕から這い出そうと必死になっていた白人兵たちの上を、容赦なく転がり、通過していく。
そして、その後方で思わず尻込みしている敵兵たちの方へ、ますます勢いを増しながら襲いかかっていった。
狭隘な道いっぱいに押し寄せていた敵兵たちは、即座には後退のしようもない。
砂煙を吐き散らしながら真正面から驀進(ばくしん)してくる巨石や巨木を前に慌てふためき、互いを押しのけようと無理に押し合うために、石木が到達するよりも早く、将棋倒しのごとく自らバタバタと倒れ込んでいった。
無数の石木が、それらの兵たちを踏み拉(しだ)いて暴走し、さらに隘路の傾斜を転がり落ちていく。
絶え間なく上がる悲痛な絶叫が虚空に吸い込まれ、紅々と燃える夕焼けを、生々しい血の色に染め上げていった。

しかし、敵の数は多かった。
ミカエラの号令により続々と雪崩来る落物攻撃の中、それでも負傷を免れた者たちや生き延びた者たちが、しぶとく前進を試みる。
彼らは激昂の雄叫びを上げ、先にも増して凶暴な形相になって、さらに攻め上って来る。
だが、再び、土砂の崩れる音と共に砂塵が嵐のように巻き上がり、多数の敵兵たちが悲鳴を上げながら二層目の塹壕へと嵌り込んだ。
その間にも、ミカエラの指揮の元、絶え間なく襲いかかり来る無数の巨石や巨木たち。
間断無いその繰り返しによって、敵軍の前衛部隊は、隊列を整える隙を一切与えられず、砲撃はもとより銃撃することもままならぬままに、ジワジワと兵力を削(そ)がれていった。
とはいえ、さすがに敵軍も強靭、且つ、執念深く、その数の多さも手伝って、そう容易く事は運ばない。
次第に幾層もの塹壕が無数の敵兵によって埋まりきってしまい、埋まっている人々を踏み台にして、新たな敵兵たちが咆哮を上げながら、本陣を敷く断崖のたもとへと烈火のごとく押し寄せ始めた。

即座に、ミカエラの厳然とした号令が、インカ軍本陣に響き渡る。
「砲撃用意!!」
今まで黙したままだった堂々たる30門の大砲が、西日に黒々と照り映えながら、その息を吹き返す。
敵軍が視界に入った冒頭の時点から、いつでも彼女の指示に応えられるよう、全砲とも眼下に向けて砲口を押し下げ、敵の前衛部隊に命中弾を浴びせんと隙無く照準を定めていた。
それらの砲列中央に進み出たミカエラは、猛々しい身のこなしで腰の帯剣を抜き放ち、決然と頭上へ振りかざした。
そして、勇ましくも艶めく声に力を込める――「全砲列!一斉砲撃!!」
振り下ろす長剣が、真紅の日射をとらえて閃光を放った。
「撃てっ!!」

雷鳴のごとき轟音が山々の大地を揺るがし、熱せられた砲弾が、突撃してくる敵兵たちの中へ猛然と飛び込んでいった。
熱弾が、敵兵の群れに次々と突き刺さる。
激しい震動でほどけたミカエラの長い黒髪が、千々に乱れ飛びながら、高々と宙に舞い上がった。
その頃、此度の決戦に派兵されたスペイン軍を総指揮する敵将ガルベス大佐は、全部隊の中央付近に身を置きながら、自軍の前衛部隊の惨状はもとより、その動揺が次第に全軍に波及していくさまを、苦々しい表情で睨みやっていた。
ガルベス大佐は、かの獅子に似た厳めしい面相と豪腕を併せ持つスペイン軍本隊総司令官バリェ将軍の側近も務めたことのある歴戦のつわものであり、そのためか、このガルベスもまた、どこかバリェに似た雰囲気を持っていた。
それでいて、ガルベスは、熱しやすく激しやすいバリェ将軍とは異なる側面――沈着冷静さをも兼ね備えた男でもあった。
彼は、前方から轟き来る絶え間無い爆鳴の中で、素早く腕を振って、己の副官を呼びつけた。
そして、立派にたくわえられた顎鬚を揺らしながら、重心の据わった声で言う。
「インカ軍は劣勢の上、退路も無い中、もう少し戦意を無くしているかと思ったが、そうでもないらしい。
ならば、ただ力押しをしていても、埒が明かん。
まずは、あの者どもの砲撃と落物攻撃を黙らせることが先決だ」

「はっ、それでは――」
そう副官が応ずるのも待たず、ガルベスは冷徹な眼光で顎鬚を擦りながら、野太い声でさらに続けていく。
「すぐに我らの野砲を集め、あのミカエラのいる中央部と、断崖の左右の三点に集中して徹底的に砲火を浴びせよ。
三方から断崖が崩れれば、あやつらの攻撃の歩調は必ず乱れる。
その隙に、崩した箇所から本陣に進攻し、早々にミカエラや息子どもを捕えてしまうのが得策であろう。
さすれば、効率良く他の抵抗も封じることができる」
壮年の貫禄を漂わせるガルベスに対して、幾分年若い副官ナダルは敬意の面差しで頷いた。
「大佐の仰せの通りに!」
「まだトゥパク・アマルの息子たちの所在は分からぬが、ミカエラが遁走せずに当地に残っていたとは、我らにとっては幸運なことだ。
あの者どもを手中に収めることができれば、トゥパク・アマルのこれ以上の暴挙を抑え、この反乱を鎮圧するための重要な要(かなめ)となる。
我らにとっても、この上無い戦果となるであろう」
ガルベスの言葉に、ナダルは素早く敬礼を返した。
「はっ!
それでは、すぐにも大々的に砲撃を実行いたします!!」
迎撃のために走り去りかけた副官の背に、殷々(いんいん)と反響するインカ軍の砲声の間を縫って、ガルベスの泰然とした声音が響いてくる。
「インカ軍の別働隊が、何を仕掛けてくるか分からん。
一定の砲を各部隊に万遍なく残しておけ」
「はっ、大佐。
心得ております!」
間もなく、ガルベスの指示通り、多数の野戦砲が隊列の前衛に集められると、本陣の方角に狙いを定めた。
「前に出すぎるな。
インカ軍の火砲の射程に入っては、このような奥地まで野砲を運び上げた苦労が水の泡だ」

ガルベスの言葉に、ナダルは「はっ…!」と答えながらも、やや困惑顔になる。
「ですが、大佐、思い切って前に出ないことには、我らの砲も、あの者どもを狙うことができません」
「それで構わん。
あの断崖上をいきなり狙うなど、上方からあやつらが攻撃してくるこの状況では不可能だ。
我らの野砲は、軽量な分、飛距離が長い。
なれば、やつらの射程外から、中央と左右の断崖中腹に集中砲火を浴びせ、やつらの足元を支える崖の中っ腹をえぐり取ってやれ」
沈着な声音ながらも語気鋭く語るガルベスに、ナダルは「はっ!」と、力強く恭順を示した。
かくして、インカ軍本陣を支える断崖の中腹部に向かって、即刻、ガルベス軍の激しい反撃が開始された。
敵の無数の野戦砲が一斉に火を噴き、いきなり何十という砲弾が、断崖中腹めがけて突っ込んでいく。
巨大な重い鉄塊が断崖の側壁に激突し、凄まじい破壊音があたりを寸断した。
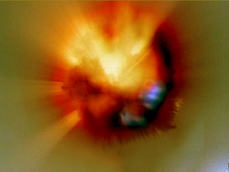
その初弾による衝撃のあまりの壮絶さに、本陣のミカエラたちは、熟練の精兵たちでさえも、数メートル後方まで弾き飛ばされた。
「――っつ……!」
ミカエラは、すかさず立ち上がろうとするが、大地震が押し寄せたがごとくに激しく胴震いする地面の上で、上半身を起こすことすらままならない。
しかも、衝撃は、その初弾のものに止(とど)まらなかった。
間髪入れず、新たな敵の鉄弾が続々と直撃し、巨大なハンマーさながらに断崖壁をかち割り、壁面を荒々しく突き崩していく。
頑強な岩や土砂が粉砕されて飛び散り、そこに生えていた木々は根こそぎ宙に弾き飛ばされ、遥か下方に霞む山麓に吸い込まれるように消えていった。
先刻のミカエラによる猛攻に復讐を図るかのように、敵の砲弾は止まることなく彼女たちの足元を揺るがし、インカ軍本陣の兵たちは、迎撃体勢を整えるどころか、まともに立ち上がることすら困難だった。
幾度と無く敵の砲口が轟然と鳴りどよもし、無数に突き刺さる鉄弾の暴挙によって、土砂はますます剥ぎ取られ、岩土が無残に砕けて弾け飛ぶ。
轟々たる地響きと共に黒炎のような砂塵がドッと沸き起こり、逆巻きながら赤黒い空へ舞い上がって、僅かな光さえも奪い去っていく。

ミカエラは、全身を打ちつけた際に切れた口内から溢れる鮮血で唇を染め上げながら、歯を食いしばり、懸命に足元を踏み締め、そして、ついに立ち上がった。
そして、彼女と同様、必死に身を起こして迎撃体勢を整えんと彼らの大砲の方へ這って行く兵たちに、まだ強い光を失わぬ面差しで力強く頷いた。
その間にも、瞬時の隙を縫って、ミカエラの目は、幼いマリアノやフェルナンドの姿を探さずにはいられない。
あたりは灼熱の煙に覆い隠され、今や透かし見ることさえままならぬ状態である。
それでも懸命に凝らす視界の先に、辛うじて兵たちに抱き起こされた息子たちの姿を見届けると、瞬間、彼女の瞳は輝きを強め、その内心で深い息をついた。
そして、同時に、彼女は周囲の兵たちにも素早く視線を馳せる。
予想以上の衝撃波によって動転はしているものの、皆、敵の反撃は覚悟していたことである。
また、断崖上を直撃されたわけではなかったことが幸いし、まだ無傷の者も多いことに胸をなでおろした。
たが、そうしている間にも、敵の砲列が火を噴き続け、絶え間ない激震と息を詰まらせる硝煙は、彼女やインカ兵たちの脳を芯から麻痺させ、その思考力を奪い去っていった。
足下の断崖壁に無数の砲弾が絶えず激しくのめり込むのを感じながら、ミカエラは血の滲む唇をきつく噛み締め、その痛みによって、霞みそうな頭を必死に澄ませようとした。
(いかに主力部隊が襲撃のチャンスを掴むまでの囮とはいえ、これほどの猛攻にさらされ続けては、さすがに持ち堪えることができなくなる――!)
何とかして反撃の機を掴もうと、幾度と無く地に打ち据えられながらも、彼女は全兵の前へと進み出て行く。
そして、全身を引き摺るようにして各自の砲の元へ戻り来た砲兵たちの姿を見定め、彼らに力強く頷くと、砲撃の号令のために長剣を高くかざし上げた。
血の滴る指先に握られた彼女の剣が、硝煙の中で鈍く光る。
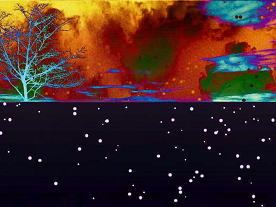
が、その瞬間、傍の大砲が、断崖下から猛烈な勢いで撃ち込まれてきた敵弾によって、凄まじい破壊音と共に弾き飛ばされた。
と同時に、ミカエラの真前で、その砲についていた砲兵たちが、悲鳴を上げる隙も無く、その身を千々に分断されて肉塊と化した。
「――!!」
飛び散る血飛沫を浴びて愕然と身を固める間にも、敵の野砲の凄まじい咆哮が唸り続け、下方から断崖上を直撃し続けてくる。
断崖の中腹を狙われたミカエラたちが最初の衝撃で動揺している隙に、敵将ガルベスの抜け目無い指揮の元、敵の前衛部隊は一気に距離を詰め、断崖の真下まで迫り来ていたのだった。
しかし、その時、敵の隊列の後衛部隊の方角から、ドッと、どよめきが上がった。
部隊中央に身を置きながら、断崖下へと攻め寄せる前衛部隊を煽り立てていたガルベス大佐は、声の上がった方角を鋭く振り返る。
他方、断崖上のミカエラもまた、爆風に霞む視界の中で、敵の後衛部隊の方向へと遠く視線を馳せた。
そして、瞬時に、ハッと大きく瞳を見開く。
いつからそこに現われていたのか、己と遥か距離を隔てた敵の背面の断崖上に、多数のインカ兵を従えて凛と立つ若者が見える!
「イポーリト――!!
なぜ…!?」
ミカエラの口元から、声にならぬ擦れ声が漏れた。
(そなたは、主力部隊を率いて、敵の側面を突くはずではなかったの……?!)
理性では当初の作戦を懸命に反芻しながらも、彼女の目は、イポーリトとその周囲の兵たちの姿に吸い付けられずにはいられない。

吹きすさぶ冷風に短マントを激しくなびかせて決然と立つイポーリトの両脇には、ベルムデスとオルティスが堅固な盾の如くに、黒光りする銃器を身構えて立つ。
その表情は、あくまで超然としており、その視線は、いかにも挑戦的な光を湛えて眼下の敵軍を睥睨している。
そして、その三人を中心に、断崖の端から端までビッシリと隙無く埋め尽くされた、銃を構えた多数のインカ兵たち。
しかも、いつの間に運び上げたのか、彼らの間には20門をくだらぬ大砲まで据えられている。
――もちろん、先のオルティスの作戦通り、それは、真の主力部隊の伏撃を援護し、本陣への猛攻を分散させるための、あくまで偽装の主力部隊であったから、実際には、そこにいるインカ兵たちは最前列に立った数十名のみで、彼らの後方は無人であったのだが……。
後方からの襲撃にも留意していたはずのガルベスであったが、いきなり背後の断崖上に現われた重装備のインカ兵たちに、苦々しく奥歯を噛み締めずにはいられない。
それらスペイン兵たちの視線は、断崖中央に立つ、ひときわ高貴で美々しい風貌をした若者へと引き寄せられた。
目を凝らせば、その若者の手には、銃とも剣ともつかぬ何か棒状のものがガッチリと握り締められている。
その時、沈みかけた夕陽の余光が一条、霊峰の狭間から射し込み、若者の手にあるものを燦然と黄金色に染め上げた。

「――!!」
その瞬間、若者の手から、瞳を突き刺す強い閃光が放射状に放たれた。
断崖下のスペイン兵たちは、咄嗟に目をすがめる。
直視できぬほどに強い煌きを放つもの――それは、まさしく代々インカ皇帝の皇位継承者に受け継がれてきた秘宝、かの黄金の笏杖であった。
そのあまりの眩しさに、ガルベスもまた、瞼を歪めて呻きを上げる。
「トゥパク・アマルの長子、イポーリトか!」
が、次の瞬間、さらに彼は己の目を疑った。
閃光の眩しさの中で辛うじて薄目を見開けば、イポーリトが立っていたと思われた場所に、今、屈強な褐色の兵たちを従えて立つ者は――!
(トゥパク・アマル?!)
眩しさも忘れて目を剥くガルベスの視線の先で、トゥパク・アマルは、そのガッシリとした長身を断崖下の敵軍に恐れ気も無く晒しながら、燃え立つような黄金の笏杖を手に、超然とそこに立っている。
両肩に巻きつけられた黒マントが斜光に赤々と染まって大きく翻り、断崖下から吹き上げる強風によって、その長髪が荒々しく宙に巻き上げられている。
(まさか…!!
トゥパク・アマルが、このような場所にいるわけがない!)
ガルベスは懸命に動揺を押さえ込みながら、わななく眼で断崖上を睨み上げた。
だが、相変わらず、そこにはトゥパク・アマルの姿がある。
しかも、かなり距離があるにもかかわらず、トゥパク・アマルの切れ長の目は、いよいよ挑戦的な眼光を強めながら真っ直ぐに己の方を見据えている。

金縛りにあったかのように身動きできずにいる敵将の視界の中で、断崖上のトゥパク・アマルは、突如、燃える笏杖を目の高さまで掲げ上げ、まるで相手を刺し貫くがごとくに、その切っ先を鋭くガルベスに向けた。
と思いきや、次の瞬間、彼は笏杖を高々と天に振り上げ、間髪入れずに振り切った。
断崖上に据えられた大砲が怒号の咆哮と共に火を噴き、鉄弾が眼下のスペイン軍めがけて突き刺さる。
大地が轟々と唸りを上げる中、多数の野砲を前衛部隊に回してしまっていたガルベス軍は、いきなり開始された背後からの砲撃に対抗するため、残されていた野砲を慌てて後衛部隊に掻き集めようとしている。
その間にも、トゥパク・アマル率いる砲列群は火を吐き続け、それらの大砲が据えられた断崖上にも、自身の大砲が吐き出す硝煙が充満していく。
その灼熱を帯びた硝煙の中で、トゥパク・アマルの荒々しいほどに力強い号令の元、彼の周囲の砲列は、いよいよ攻撃の激しさを増していく。
苛烈な砲撃の連続にガルベス軍が反撃をまごついているさまを冷ややかに見下ろしながら、トゥパク・アマルが再び黄金の笏杖を振り上げる。
その時、彼を目がけて、二閃、三閃、断崖下から銃火が鋭く噴き上がった。
だが、到底、銃弾の届く距離ではなく、弾は逆巻く冷風の渦中に塵のように呑み込まれただけだった。
その様子をいっそう冷徹な眼光で見下ろすトゥパク・アマルと、銃撃の起こった方角とを睨みながら、未だ混乱から抜け切れぬガルベスが、副官の腕を乱暴に掴み上げた。
「考え無しに撃たせるな!!
トゥパク・アマルは生け捕りにしろとのアレッチェ様のご命令である!
そのことは、全兵に行き渡らせているはずだ!」
興奮して声を軋らせるガルベスに、副官ナダルは驚いて目を見張った。
「トゥパク・アマル?
な、何のことです?」
「何を惚けたことを言っておる!
あそこのトゥパク・アマルを撃つなと言っておるのだ!!」
普段の冷静な上司ガルベスの尋常ならざる激昂ぶりに戸惑いながら、ともかくもナダルは指差された方角を見上げた。
しかし、そこでは、先ほどからイポーリトが笏杖を手に砲撃の号令をくだしているばかりである。
「大佐、どこにトゥパク・アマルがいると言うのです?」
平素から決してガルベスに礼を失することのないナダルであったが、この時ばかりは、その声音に、この緊急時に何を訳の分からぬことを言っているのかとの苛立ちが滲む。
そして、今、ナダルに向いていた顔を再び断崖上に振り向けたガルベスの視界の中にも、もはやトゥパク・アマルの姿はどこにもなかった。
「――…!」
ガルベスは、汗の噴出した顔を手の平で拭う。
その様子を見やりながら、ナダルが不審気に問う。
「大佐、一体、どうされたのです?」
「いや、気にするな…」
(あれが、ただの幻影だったと……?!)
ガルベスは混乱から抜け切れぬまま、だが、もっと冷静なはずの己が何を血迷っているのかと自嘲せずいはいられない。
そもそも、英国艦隊との決戦に今しも臨まんとしているトゥパク・アマルが、このようなところにいるわけがないではないか!
そう苦笑しながらも、しかし、彼の心は硬く冷えていた。
(だが、あの男は、何を仕出かすか分からぬという不気味さがあるのだ……!)
しかも、先刻のトゥパク・アマルの挑戦的な面差しが、いやに生々しく脳裏にこびりついて離れなかった。

しかし、忌々しい想念を己の意識から引き剥がし、ガルベスは周囲の状況に険しい目を向けた。
自軍の後衛部隊は、やっとのことで野戦砲による反撃を開始しているものの、イポーリトたちの攻撃によって被害はみるみる広がりつつある。
そうしている間にも、断崖上では、イポーリトが高々と黄金の笏杖を振り上げ、火炎の照り返しに頬を染めながら敢然と号令を放ち続けている。
「発射用意!!」
朱色に燃え立つ笏杖が振り下ろされる。
「撃てえ!!」
イポーリトが擁する20門の全砲が咆哮し、猛然と眼下の敵に挑んでいく。
絶え間なく繰り広げられる怒号の砲撃と地響きの中で、副官ナダルは硝煙に霞む眼を、ガルベスに向けた。
「大佐……!
敵の主力部隊は、ミカエラの方ではなく、あのイポーリト?!」
「いや、もしや、あれも――」
どうにも嫌な予感に憑かれ、厳しい表情でガルベスが何かを答えようとした。
が、その時、ミカエラの護る本陣からも凄まじい轟音が炸裂し、ガルベスの野太い声を掻き消した。
ミカエラ軍が、息を吹き返したかのように、果敢な砲撃と石木攻撃を再開したのだった。

イポーリト軍の出現によって、スペイン軍の意識がそちらに向いた一瞬の隙に、ミカエラたちは、すかさず臨戦態勢を建て直していた。
前後からミカエラ軍とイポーリト軍の攻撃が勢いを増したさらにその時、突如、宙から湧き出すがごとくに、褐色の大軍勢がスペイン軍の隊列に両側面から襲いかかってきた。
伏撃攻撃を仕掛けんと、隘路に誘い込んだスペイン軍の両翼斜面に潜んでいた真のインカ軍主力部隊が、時を得て、ついに出撃してきたのであった。
スペイン兵たちが、反射的に銃を向ける。
だが、周囲は息詰まる爆風と硝煙に覆い尽くされており、まるで濃厚な煙幕を張り巡らされたかのように視界が悪い。
その瞬間にも、褐色の兵たちは野性の敏捷さで急斜面を滑り下り、生きた落石さながらに猛然と敵軍の中に飛び込んでいく。
鈍器を振り回して白人たちの手にある銃を弾き飛ばしながら、続々と降り注ぎ、沸き踊る――それらインカ兵たちのむせかえるような人熱(ひといき)れと雄叫びに呑まれ、スペイン兵たちは混乱状態に陥った。
しかし、それも束の間のことであった。
ガルベスによって精神的にも肉体的にも鍛え上げられてきた敵軍は強靭で、すぐさま剣を抜き放ち、鋼の甲冑をギラつかせながら猛々しく応戦してきた。
日没迫る深山の地に、剣や刃の放つ血生臭い閃光と無数の金属音が充満していく。
槍と剣が切り結ぶ音。
戦斧が鋼の鎧を突き破る音。
棍棒が銃身を叩き潰す音――!!

しかし、あまりに至近距離での斬撃の応酬となり――それは敵の銃撃を封じるためのインカ軍の目論み通りではあったのだが、断崖上のミカエラやイポーリトは、眼下の戦況が白兵戦に突入した今、味方を撃つ危険を冒すことはできず、砲撃や落物攻撃を中止せざるを得なかった。
「撃ち方、やめえ!!」
前後の断崖上でミカエラとイポーリトの号令が響き渡り、高熱を帯びた砲口たちが、硝煙の残滓(ざんし)を吐き出しながら沈黙した。
すかさずイポーリトが兵たちを振り返る。
「ベルムデス、オルティス、みんな!!
僕たちも戦いに加わるぞ!!」
イポーリトの言葉に、ベルムデスもオルティスも、兵たちも、「はっ!!」と即座に恭順を示す。
彼らは、必要に応じて砲撃を再開できるよう必要最低限の砲兵を残し、速攻、断崖を駆け下りていく。
全速力で疾駆する彼らの耳に、インカ軍の士気を鼓舞するホラ貝の音が高らかに木霊する。
全身に熱い血潮がたぎり、己がまともな実戦経験の無いことなど、今、イポーリトの頭からは完全に消えていた。
激しい乱戦の展開されている戦場の渦中を目指して、鋭利な横顔で疾走するイポーリト。
その足の非常な速さと動きの鋭敏さに、彼の横を走るオルティスは、密かに驚きを禁じ得なかった。
だが、思い起こせば、彼の父トゥパク・アマルも、その俊足や攻撃速度の速さが特徴でもあった。
(血は争えない――!)
己の足でさえも遅れを取りそうなほどの速さと美しい身のこなしで、断崖を飛び降りていく皇子の姿に、オルティスは内心で微笑み、それから、険しい横顔になって前方へ意識を戻す。
もう、すぐ眼前に、血飛沫の飛び交う白兵戦の修羅場が迫っていた。

その中央めがけて、まっしぐらに突き進みながら、すかさず腰のサーベルに手をかけて勢い良く抜き放ったイポーリトに、オルティスが鋭い声で言い放つ。
「イポーリト様!
決して、わたしから離れてはなりません!!
あなた様は、最も敵の標的にされることをお忘れなく!!」
今や完全に戦闘モードに入っているイポーリトは、オルティスの言葉が聞こえているのかいないのか、声を発することなく形だけは頷いた。
が、それと殆ど同時に、敵の猛攻に押されて斬りかかられているインカ兵と敵兵との間をめがけて真っ向から突っ走って行く。
「あ……!
イポーリト様!!
お待ちを!!」
オルティスは、戦斧と見紛うほどの巨大な半月刀を抜き放ち、疾走する皇子の姿を慌てて目で追った。
(皇子に離れるなと言うより、自分が皇子から離れないようにすることの方が現実的か…!)
彼は、はやくも四方から襲い来る敵を薙ぎ払いながら、イポーリトの後を追おうとする。
しかし、その間にも、怒涛の混戦状態の中で、二人の間には、たちまち多数の敵兵たちが鉄壁のごとくドッと雪崩れ込む。
一方、その間にも、イポーリトは疾風の速さで、敵兵が大きく剣を振り上げた先の地面に倒れ込んでいるインカ兵の前に飛び込んでいく。
次の瞬間には、彼のサーベルが火花と共に宙を切り裂き、振り下ろされた敵の刃をガンッと受け留めた。
戦場に、ひときわ甲高い金属音が響き渡る。
「イ、イポーリト様!?」
すかさず飛び込んできて己の瀕死の危機を庇ってくれたのが、まさか皇子であろうとは――!!
歓喜を通り越して仰天しているインカ兵の前で、しかし、イポーリト自身は、敵の刃を己の剣で受け留めたまま、みるみる相手の力に押されていく。
他方、いきなり目前にトゥパク・アマルの息子が飛び出して来ようとは、相手のスペイン兵も驚きに目を剥いていた。
だが、少し冷静になれば、これほど美味しい獲物も無かった。
敵兵の眼が爛々たる光を放ち、いよいよ獰猛な力でイポーリトの剣を押してくる。
そうしている間にも、地に倒れていたインカ兵が、すぐさま体勢を建て直し、群がるように襲い来る敵兵たちをイポーリトの周囲から槍で打ち払っていく。
しかし、当のイポーリト自身は、敵の剣を受け留めたまま、血が滲むほどに歯を食いしばって相手の怪力に耐えていた。

「くっ……!」
まだ少年のイポーリトと豪腕の大人とでは、力そのものの差がありすぎる。
その時、敵の眼が残忍な光を放ち、と同時に、イポーリトの腕から、今まで恐ろしい怪力で押しかかられていた相手の力が不意に抜けた。
と思いきや、まだ剣を受け留めた体勢のままであった皇子の虚を突くように、突如、相手は刃を下に引き下げると、いきなり下からイポーリトの下腹部めがけて突き上げてきた。
「――!!」
が、それより僅かに早く、数メートル先からオルティスが投げ放った刀が、敵の背部に突き刺さった。
驚愕して目を剥くイポーリトの前で、口から血を吐きながら、敵兵が、ドゥッと地に崩れる。
見れば、オルティスの巨大な半月刀が、鋼の甲冑の隙間から、敵の頚部を貫通していた。
突き刺さったままの半月刀が、地獄の鎌のごとく真紅に染まっていく。
「―――…!!!」
地に伏した敵の亡骸の背後から、すぐさまオルティスが駆け寄ってきた。
長い髪を逆立て、険しい形相をした彼の全身からは、まだ強い殺気が漲っている。
だが、イポーリトに向いたその眼差しには、深い安堵が滲みだす。
「イポーリト様、ご無事で!」
「オルティス、あ、ありがとう……」
敵の吐血と返り血を全身に浴びて、呆然とも愕然ともつかぬ表情の皇子が、擦れ声で答えた。

彼にとって、実際に眼前で人が息絶える姿を目の当たりにするのは、これが初めてのことである。
そんなイポーリトの目の前で、オルティスはグッと力を込めると、地に伏した屍から一気に刀を抜き取った。
再び飛散する血飛沫に、イポーリトは咄嗟に大きく退いた。
一方、オルティスは、厳めしい表情を振り向かせ、皇子を見た。
「イポーリト様、敵将ガルベス大佐は、先刻の砲撃で崩壊させた断崖壁を伝い登り、本陣へ攻め込まんと狙っているものと思われます。
ミカエラ様や本陣に残っておられる皇子様たちの御身が危険です。
この白兵戦の最中を斬り進まねばなりませんが、我らも急ぎ本陣へと向かいましょう!」
しかし、そう語る先から、イポーリトめがけて、とどまること無く新たな敵の刃が襲い来る。
すぐさまオルティスが皇子の前に飛び込み、真紅の半月刀を振りつけ、まるで斧を打ち込むがごとくに、敵の胴体を鎧ごと叩き斬った。
相手が絶叫と共に倒れ込むよりも早く、オルティスは次なる標的へと向きを変える。
かたや彼の眼光を受けた敵兵たちは、辛うじて剣を握り締めてはいるものの、凄まじい刀に分断されたばかりの同輩を前にして、狼に射すくめられた兎よろしく立ち竦んでいる。
その隙にも、オルティスの刀が電光を散らし、皇子の周囲からスペイン兵たちを猛烈な勢いで薙ぎ払っていく。
いつしかオルティス配下の精兵たちも、怒涛の敵群れを突破して、イポーリトの周囲に集まってきていた。
彼らは円陣を組んで皇子を護りながら、各々、得意の武器を鋭く唸らせている。
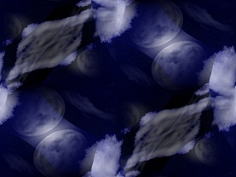
他方、イポーリト自身も、返り血で染まったその手に、今一度、サーベルをグッと構えた。
今も、先刻の衝撃を引きずったまま、気持ちは激しく波打ってはいた。
だが、実際に体を使って剣を振るいだしたことや、オルティスをはじめとする周囲の兵たちの機敏な動きを肌身で感じ取りだしたことで、戦闘の勘のようなものが己の身内に沸き上がりくるのを感じてもいた。
イポーリトは心を澄ませようと、腹部まで深く息を吸い込んだ。
(落ち着け…!
今は、恐れたり、躊躇(ためら)ったりしている時じゃない……!
何としたって、この一戦に勝たなければ、父上や母上が今までやってきたことも、僕たちを信じてついてきてくれたインカの民の苦労も、みんな台無しになってしまうんだ!!)
その時、味方の護りを斬り伏せた巨躯の敵兵が、大きく上段に剣を振りかぶってイポーリトの方へ突進してきた。
「――!!」
戦慄が背筋を走ったが、そのような心の反応よりも早く、イポーリトの身体は斬り込んでくる相手の剣の下を反射的にかいくぐっていた。
その動作は、まるで一陣の風が吹き抜けたような非常な素早さで、大柄な敵兵は、一瞬、その平衡を失って、体を僅かによろめかせた。
その瞬間を逃さず、皇子は相手の胴体をサーベルの柄で思い切り突きのけ、相手がさらにバランスを崩したところを、甲冑から覗く顎下めがけて、ひと思いに下から剣を突き立てた。
悲鳴ともつかぬ擦れた咆哮を上げながら、敵兵がのた打ち回る。
己が剣を突き立てておきながら、相手の苦悶の激しさに、思わずイポーリトは後ずさる。
そこに走り込んで来た周囲のインカ兵たちが、一気に止(とど)めを刺した。
「皇子様、お見事でございます!!」

兵たちの言葉に返事を返すこともできぬまま、ただガクガクと不自然に頷くと、イポーリトは血で染まった剣を握り締めて次の襲来に構えた。
が、剣を握る指先が激しく震えている。
チラリと視線を馳せれば、先刻の敵兵が血の海の中に倒れ伏しているのが、薄闇の中でもはっきりと分かった。
人間の体の中には、こんなにも血が入っているものなのか――!!
イポーリトの背筋と心の芯を、突き刺すような悪寒と悲愴感が走り抜けた。
戦場に逆巻く狂気の渦の中で、あまりに様々な感情が押し寄せ、大きく微動するイポーリトの瞳に涙が滲む。
気付けば、いつしか離れ離れになっていたベルムデスが、彼の傍に戻っていた。
血糊で染まった悲痛な表情のイポーリトに、ベルムデスは、ただ黙って深く頷いた。
それから、また敵兵の大波に押されて千々バラバラになってしまったオルティスや彼の精兵たちの代わりに、すぐに皇子を護るようにして、すかさず敵襲に構えた。

二人で本陣の方角目指して懸命に道を斬り拓きながらも、ベルムデスの老練な横顔を伺えば、普段の温厚な彼とは別人のように厳めしい戦士の風貌をしている。
険しく吊り上った眼は炯々と光り、隙無く辺りを睨み据えている。
厳つい体躯は筋肉が引き締まり、その強靭で鋭敏な動作とあいまって、イポーリトの目には、到底、60歳を超えているとは思えなかった。
実際、ベルムデスは、その智慧によってトゥパク・アマルやミカエラの相談役を果たしてきたのみならず、つい先般のトゥンガスカの本陣戦でもトゥパク・アマルと共に戦場を駆っていた、現役の戦士でもあったのだ。
既に幾つもの傷跡を刻んだベルムデスの逞しい両の手には、今、右に重厚な長剣が、そして、左に黄金の笏杖がガッチリと握られている。
イポーリトの強い視線を感じて、ベルムデスが片目だけ皇子の方へと振り向いた。
そして、その目元に皴を寄せて微笑む。
「イポーリト様、先刻、兵を救われた御姿、確かに、この目におさめましたぞ。
父君や母君にも、お見せしとうございました!」
「ベルムデス……!」
祖父にも等しく思っているベルムデスの言葉に、数々の激しい衝撃から未だ抜け切れぬイポーリトは、いよいよ目頭を熱くした。
その時、突如、上方から強い殺気を覚えた。
上からの不意打ちを狙った敵兵が、剣を振りかぶり、山の斜面上方から二人めがけて飛び降りてきたのだ。
「あ――!!」
反射的にイポーリトが身を翻した時には、ベルムデスの気を凝らした鋭い息遣いと彼の剣の唸りだけが頭上で聞こえ、次の瞬間には、ベルムデスの豪腕が、早くも敵兵を斬り伏せていた。
と見るや、その恐ろしく熟練した身のこなしで、さらに上方から飛び込んできた敵兵に向かって、もう一閃、強烈な一撃を見舞って息の根を止めた。

本来の年齢には到底見えぬベルムデスの猛烈な凄腕に、イポーリトは、驚愕と恍惚の表情で息を詰める。
若い己自身の呼吸さえ既にかなり上がっているというのに、ずっと激しく動き続けているベルムデスの息遣いは落ち着いたものだ。
周囲の喧騒を忘れたかのように、穴の空くほどに己に見入っている皇子の耳元に、ベルムデスがサッと顔を寄せた。
「イポーリト様、敵は、あなた様やミカエラ様を生け捕りにしたいのです。
さすれば、トゥパク・アマル様を脅迫するための人質とすることができますからな」
「……―!」
「ですが、裏を返せば、よほどのことが無ければ、お命までは狙ってこないと言えましょう。
実際、あなた様に向けて銃を発砲してくる兵はいない。
とはいえ、流れ弾には、十分ご注意頂かなければなりませんが。
それに、もう間もなく完全に日も落ちる。
夜の闇は、味方撃ちを避けるため、敵の火気をさらに封じることができましょう」
そう早口で語る間にも、絶えず襲い来る敵の斬撃から皇子を庇うベルムデスの長剣が、さらに加速しながら唸り続ける。
二人の周囲でも、敵味方入り乱れた兵士たちが、打ち合い、斬り合い、叩きつけ合いながら、各々、己の敵を倒そうと躍起になって武器を振るっている。
茫漠と闇に舞い上がる砂塵の中で、イポーリト自身も、己に突き込まれてくる敵の刃を必死にかわしていた。

敵襲に備えて皿のように見開き続けてきた目に、砂塵や汗や血が沁みて、瞼を開けていることさえ難儀である。
彼は、渇ききった喉を軋らせて声を発しようとするが、ハァハァと喘ぎ続ける息遣いが激しくなるばかりだ。
それでも、脇で長剣を振るうベルムデスに向けて、懸命に声を振り絞った。
「ベルムデス!!
一体、戦況はどうなっているんだろう?!
こんな混戦状態じゃ、どっちが優勢なのかも分からない……!
もう、こんな――…」
先の見えぬ戦いには耐え切れない!!もう力尽きそうなんだ!!――ベルムデスの厚い庇護に甘えて、つい、そう叫びそうになってしまった己の弱音を、イポーリトは必死に噛み殺した。
一方、皇子の言葉に、その鋭敏な動きを休めることなく、ベルムデスは重々しく頷き返す。
「断片的ながら伝わってくる報告によれば、現在、戦況は、五分と五分というところでしょう。
先刻のミカエラ様やイポーリト様の断崖上からの砲撃によって、敵の前衛部隊と後衛部隊には相応の被害を与えたものの、敵の絶対数が多すぎます。
側面からの伏撃も効果はありましたが、致命的な打撃を及ぼすまでには至らず――」
そこで二人の間に狂ったように分け入って来た敵兵に、すかさず鋭い報復を見舞い、再びベルムデスが言葉を継ぐ。
「さすがにバリェ将軍直下のガルベス大佐率いる精鋭軍だけあって、敵も良く鍛えられていると言わざるをえません。
これほどの険しい山岳地を登って来たというのに、その疲労も思いのほか見せてはいない…!」

険しい眼光で口惜しげに語るベルムデスの言葉に、イポーリトは顔を強張らせた。
そんな皇子の気配を察して素早く横目を走らせたベルムデスの視界に、絶望的な目をした一人の少年の、汗と血糊にまみれた横顔が映る。
「まだ…五分と五分?!
それじゃ、あとは、この白兵戦次第ってこと?!
どちらかが降伏するか全滅するまで、僕らは延々と戦い続けなければならないと……?!」
口の中があまりに渇いて呂律が回らず、不意にイポーリトは大きく咳き込んだ。
口内にも血や埃が張り付いて、言いようもなく不快そのものだ。
その上、肺も、戦塵と硝煙を吸いすぎたために、猛烈にひりついている。
「つぅ……」
ここまで生き延びることに必死で、今まで忘れていた全身と内側からの激しい痛みが、急に生々しく神経に沁みてきて、イポーリトは思わず呻いた。
彼の視線が、苦渋を帯びて不安定に宙を彷徨う。
人で充満した狭隘な山道では、本陣に向かって押し寄せんとするスペイン兵の波と、それを阻止せんとするインカ兵の波とが激しくぶつかり合っている。
双方、引いては押し寄せるの一進一退で、その間中、鋼の打ち合う音と、不規則に弾ける銃撃の音とが、濃さを増す闇の中に殷々と響き渡っている。

果たして、本陣はどうなってしまっているのか?
一刻も早く駆けつけねばと気は逸りながらも、今は、それらが全て、どこか遠くで起こっている絵空事のようにさえ思えてくる。
殺意に満ちた大波に揉まれて今にも崩れそうなイポーリトに、彼を護って戦い続けるベルムデスが、その視線で勇気づけるように力強く周囲を指し示した。
「イポーリト様、どうかご覧くださいませ!」
イポーリトが朦朧としかけた視線を上げれば、相変わらず勢い良く戦い続ける無数のスペイン兵たちの姿が目に飛び込む。
だが、それら敵兵たちと死闘を繰り広げるインカ兵たちとて、まだ勢いや粘りを失っているわけではない。
しかも、味方の兵たちは、討ち合いと討ち合いの瞬時の狭間に、懸命にこちらに視線を送ってくる。
傷つき、疲弊し、果てしない激しい戦闘状態の中で、彼らの目は、戦う皇子の姿を懸命に追っているのだ。
ベルムデスの深く篤い声が、耳元で響く。
「インカ兵たちは、あなた様がここで戦っておられる御姿を励みに、猛烈に奮戦しておりますぞ。
イポーリト様、どうかあなた様の兵たちをお信じください!」
「ベルムデス……」
イポーリトは歯を食い縛って、目の汗を拭った。
そして、鉛のように重い腕を持ち上げ、再び剣を構えようとする。
だが、その瞬間、視界を遮る薄闇の向こうから、突如、刃だけが繰り出され、イポーリトめがけて鋭い突きが目前に迫った。
「うぁっ!!」
天賦の敏捷さで、イポーリトは憔悴したその身をギリギリかわした。
敵の刃が首筋をかすめ、艶やかな黒髪がズバッと耳下で切れて夜風の中に舞い散った。
無理な体勢で相手の剣をかわした皇子の体が脇によろけた隙に、闇の中から刃の主であった敵兵が姿を現し、その剣を大きく振りかぶった。
「――!!」
イポーリトが声にならぬ叫びを上げる。
が、それより僅かに早く、脇にいたベルムデスの左手にある笏杖が一閃し、即座に敵の胴体を叩き付けた。
木に斧を打ち込むような強打音が、イポーリトの鼓膜に木霊する。
その時には、ベルムデスの右手の長剣が、バランスを崩した相手の頸部を貫いていた。
しかし、息つく間も無く、次の瞬間には、砂塵に霞む四方から、さらに多数のスペイン兵がドッと飛び出し、一斉にイポーリトに向かって突進してきた。
四方から押し迫る敵を前にどう対処すればよいのか、もはや疲弊しきったイポーリトの頭は即座に判断することができなかった。
頭が真っ白になるのを感じながら、為す術も無く、愕然とその場に凝固する。
その時、彼は、己の目の前に、闇よりも濃い大きな影のようなものが不意に現れたのを感じた。
その影は、イポーリトを護るようにして、こちらに背を向け、押し寄せる敵群れと彼との間に厳然と立ちはだかっている。
